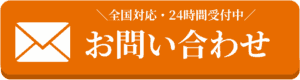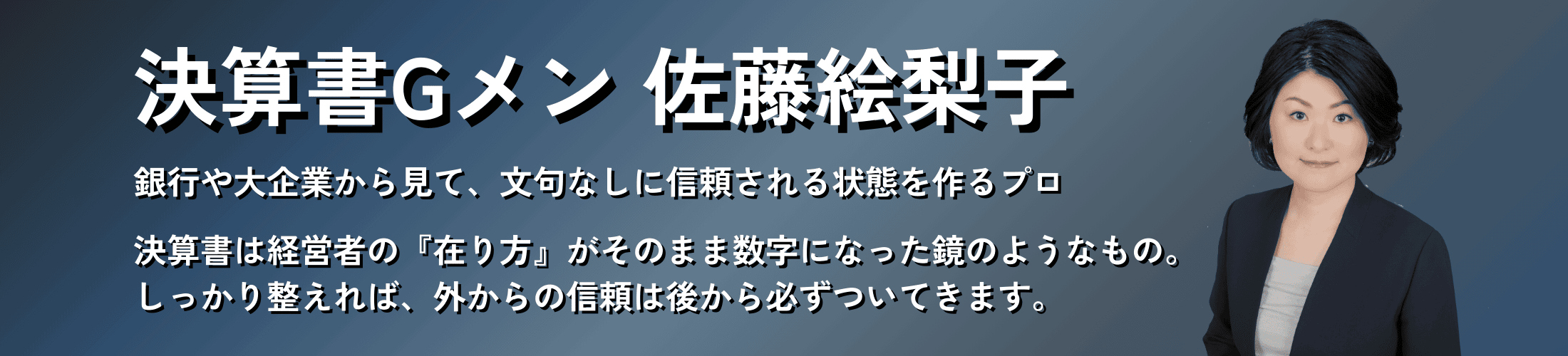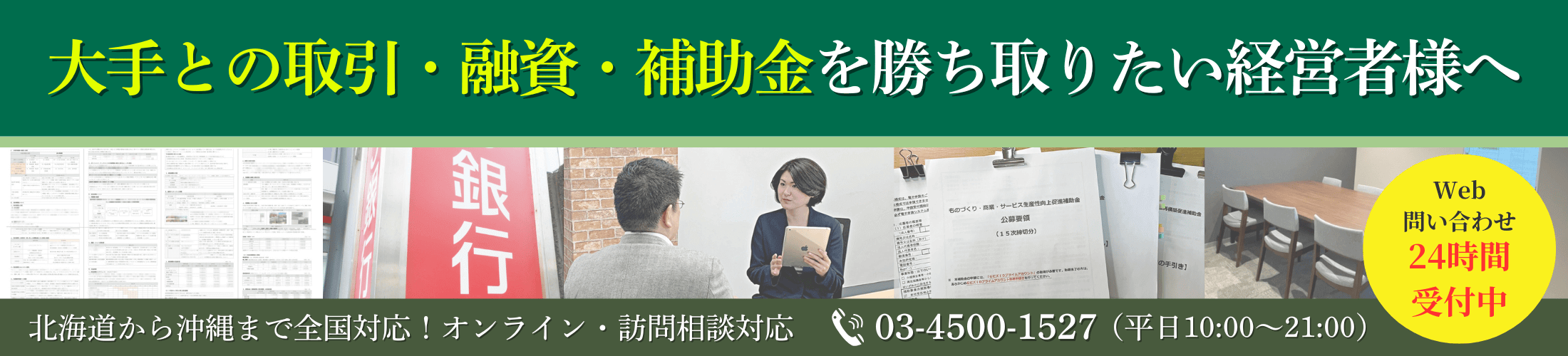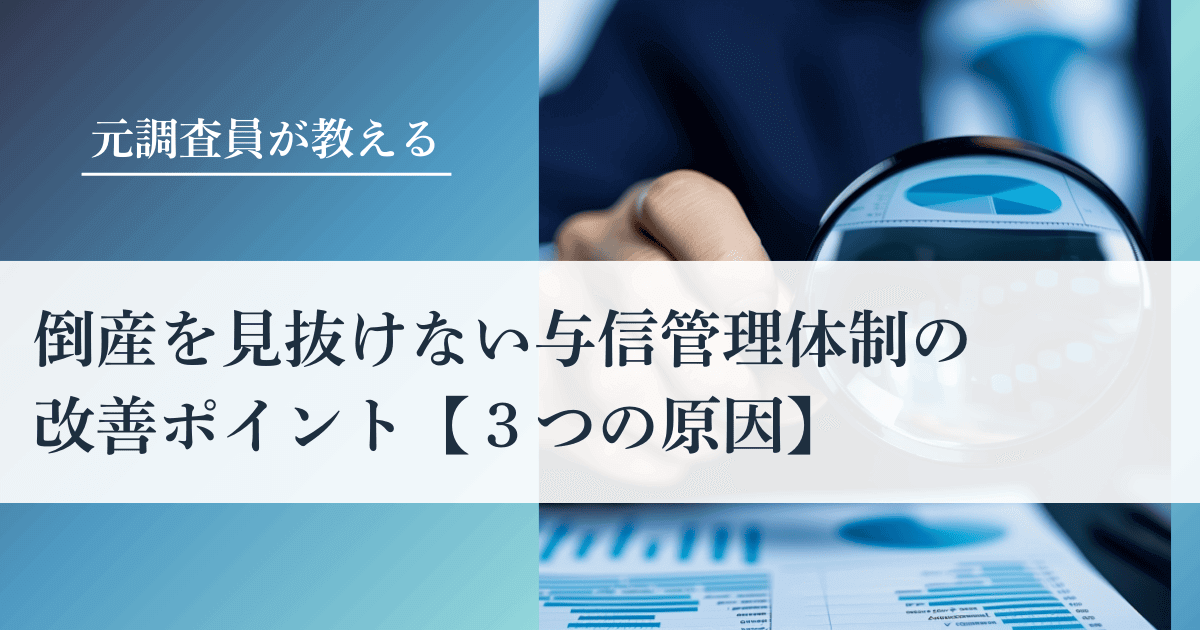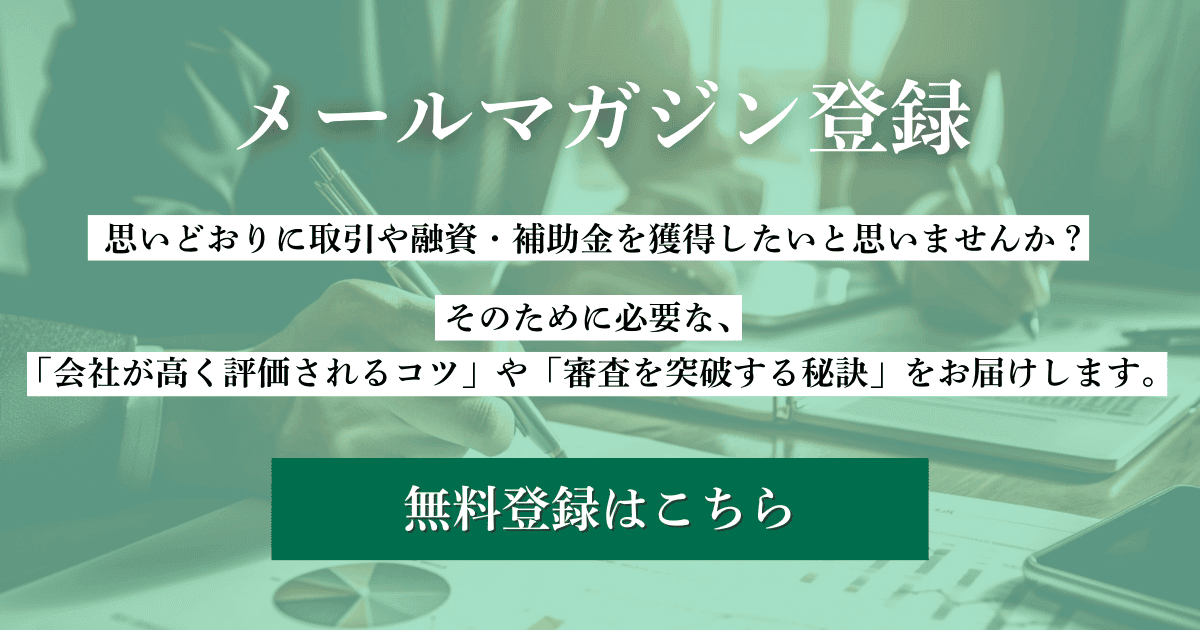与信管理をしているのに、取引先の倒産の兆候に気づけなかった。
今までと状況が変わっていたが、それが倒産の兆候だとは思わなかった。
要注意先として見ていたが、対処を検討しているうちに倒産してしまった。
もし皆さまの会社がこのような状況なら、その与信管理体制には問題があります。
日々の確かな与信管理がなければ、いざという場面で倒産を見抜くことはできません。
本記事で解説する「倒産を見抜けない与信管理体制の改善ポイント」を参考に、見抜けない原因を探り、体制を強化していきましょう。
この記事を書いている私のプロフィール
 佐藤絵梨子(さとうえりこ)
佐藤絵梨子(さとうえりこ)
会社信用ドットコム代表・会社信用クリエイター
世界最大の企業情報を保有する (株)東京商工リサーチに入社後、個人から売上1兆円企業まで10年間で延べ7,000社以上を調査。商業登記簿から会社の信用度を見抜くほどになり、全国1,000人以上の調査員中、営業成績1位獲得の実績を誇る。2017年同社を退職。現在は大手企業との取引実現から銀行融資・補助金獲得まで支援するサービスを展開。小さな企業の救世主として期待されている。
*経済産業省認定 経営革新等支援機関(認定支援機関ID:107713006411)
倒産を見抜くのが難しい理由

倒産を見抜くのは簡単ではありません。
実際、元調査員の私でも、状況判断に苦慮するケースを何度も経験しています。
見抜くのが難しいのは、「情報隠しが起こる」「正しい状況判断が難しくなる」という2つの現象が起こるからです。
経営者は経営悪化を外部に見せないように全力を尽くします。取引先や銀行との関係悪化も表には出にくいものです。年に1度の決算ではじめて取引先の状況悪化に気づくことは少なくありません。
逆のケースもありますね。
経営者が回復を信じて精力的に動き、一時的な好転を見せるのです。実際にはすでに手遅れで、無理な対策が続かず状況改善には至らないことも多いのですが、一時的な好転に期待感を持っている間に倒産してしまったと嘆く営業マンや審査担当者は数知れません。
限定的な情報や、錯綜する情報から、その企業の“本来の危険度”を正しく見抜くには、日々の高度な与信管理が欠かせないのです。
そのために、普段から体制を強化しておく必要があります。
倒産を見抜けない与信管理体制の改善ポイント【3つの原因】
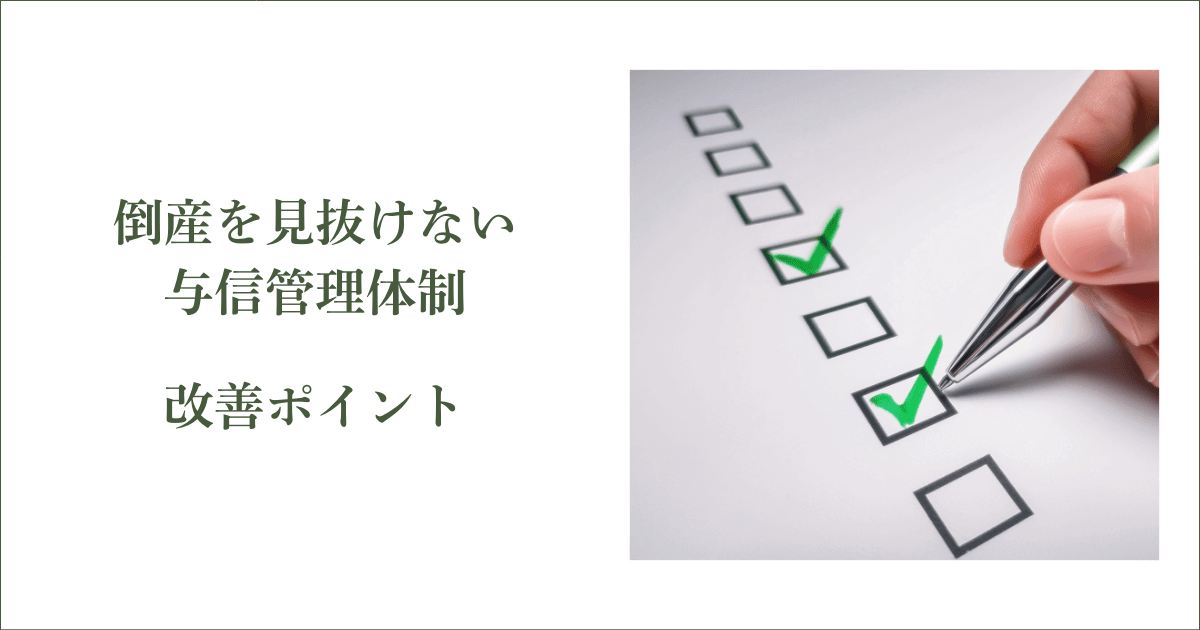
普段から与信管理をしているのに倒産を見抜けない場合、「情報収集」「与信判断」「管理体制・運用」のどこかに問題があります。1つずつ確認していきましょう。
情報収集の改善ポイント
情報収集は、情報の「不足」「正確さ」の2つの視点から改善が必要です。
情報の不足
取引先の与信判断は、情報を十分に集めることから始まります。ここで1番避けたいのは、情報の『不足』ですね。現状や変化を把握できなくなり、倒産のような難しい与信判断はとくに難しくなります。
情報不足は、自社の情報網だけに頼っていると起こりやすいです。信用調査会社の報告書、許可登録・官報等の公開情報など、複数の情報源から十分に情報を収集できているでしょうか?
情報収集の頻度が低い場合も、情報不足が起きやすいです。目安としては、要注意な取引先は半期に1度、より注意が必要な取引先は四半期に1度のペースで情報を収集し、最新の情報を網羅的につかむべきです。情報不足のまま過去データに依存すると、倒産はますます見抜けなくなります。
情報の正確さ
集めた情報が「信頼できるか」「正確か」の確認はできていますか?真偽不明な情報や、裏付けがない情報をもとに判断すると、判断を誤り、倒産も見抜けなくなります。
情報不足に注意している審査担当者の方は多いですが、情報の正確さまで厳しくチェックできている方は少ないように感じます。ご注意ください。
複数ルートから情報収集をして情報同士の照合をしていない場合、取引先や現場に近い筋からの情報収集が甘い場合、そもそも普段から整合性を確かめるチェックをしていない場合は、正確な情報を収集できず、倒産を見抜けない事態になりやすいです。
与信判断の改善ポイント
取引先の正確な情報を十分に収集できていたとしても、与信判断が上手くいかなければ台無しです。与信判断の改善ポイントは「分析の精度」「取引実績と経験則への依存」の2つの視点で確認してください。
分析の精度
皆さまは高レベルな企業分析ができているでしょうか?ほかの審査メンバーも含め、担当者個人の分析・判断レベルを確認しましょう。
「経営状況や財務から倒産の危険性を正しく判断できるか」「倒産兆候を読み取る能力があるか」「類似ケースや取引実績を分析に反映する能力があるか」「担当者間で分析結果に大きなばらつきがないか」という視点で確認が必要です。
倒産前は情報が隠されることも多いですから、取引先から得た直接情報だけでなく、「外部情報や第三者情報だけから危険性を推察できるか」という視点でも確認をしておきたいところです。
例えば、商業登記簿や不動産登記簿の変遷から取引先の危険度を判断できますか?「わからない」と感じた方は、分析レベルが低い可能性がありますので要注意です。
取引実績と経験則への依存
過去の類似ケースや取引実績、経験則を分析に反映させることは大切です。ただし、頼りすぎは禁物。判断を誤ることがあります。とくにベテランの審査担当者が与信判断をする場合や、古くからの取引先が多い場合に起こりやすいケースですね。
先日インタビューを受けた記事でもお伝えしたのですが、実はいま、経験値や過去の取引実績に頼った与信判断をすることは大変危険です。これまで経験したことがないコロナ感染拡大という事態が起こり、そしてコロナ融資で延命した企業も多く、倒産可能性や、その時期が読みにくくなっています。
過去の取引実績や経験則は当てはまらなくなっていますので、事業環境の変化をとらえた与信判断ができているかも、しっかり確認してください。
管理体制・運用の改善ポイント
情報収集や与信判断が適切であったとしても、その結果を組織的に活用する仕組みや運用体制が整っていなければ、倒産は見抜けません。大企業でこの管理体制・運用面に穴があることが多いです。
管理体制・運用の改善ポイントは、以下の2点から確認してください。
組織として情報や判断を活かす仕組み
意外と多いのが、社内の情報共有ができていないケースです。例えば、審査部だけで情報を管理していて、営業部や調達部、法務部など他部署の情報が統合されず、与信判断に反映されない状況がそうですね。取引現場に近い情報は大変貴重で正確性も高いです。判断情報に含めなければ、倒産を見逃してしまうでしょう。
情報が責任者や経営層に共有されず、いつまでも最終判断ができないケースも見かけます。
そもそも、判断をする責任者や対処法が曖昧になってはいませんか?「取引先が危ないかもしれない」という警戒情報や異常値をつかんでも、いつまでも誰も危ないと断定しない、担当者不在で対処不能となれば、結果として倒産前に与信判断ができない可能性が出てきます。
継続的な管理体制
今現在、与信管理でとくに問題が出ていないとしても、それが将来まで続くかどうかは検証が必要です。
そもそも、皆さまの日々の与信管理では、倒産に近い状況の企業を目にする機会はあまりないのではないでしょうか?個々の審査担当者の倒産分析の目を鍛えるような対策をしておかなければ、情報収集の精度も分析レベルも上がらず、いざという場面で倒産を見逃す危険性は高まっていくでしょう。
例えば、過去事例の共有や研修の受講、定期的なモニタリングや評価の仕組みなど、組織として整えているでしょうか?今はなくても大丈夫でも、審査メンバーの入れ替わりや事業環境の変化によって、将来的には必ず問題が出てきます。
また、倒産前の企業は急激に状況が変わることも珍しくありません。変化をつかむために短いスパンで情報収集と判断をしていくモニタリングや評価の仕組みがなければ、倒産を見抜くことはできません。
元調査員の私が倒産予測で感じた恐怖
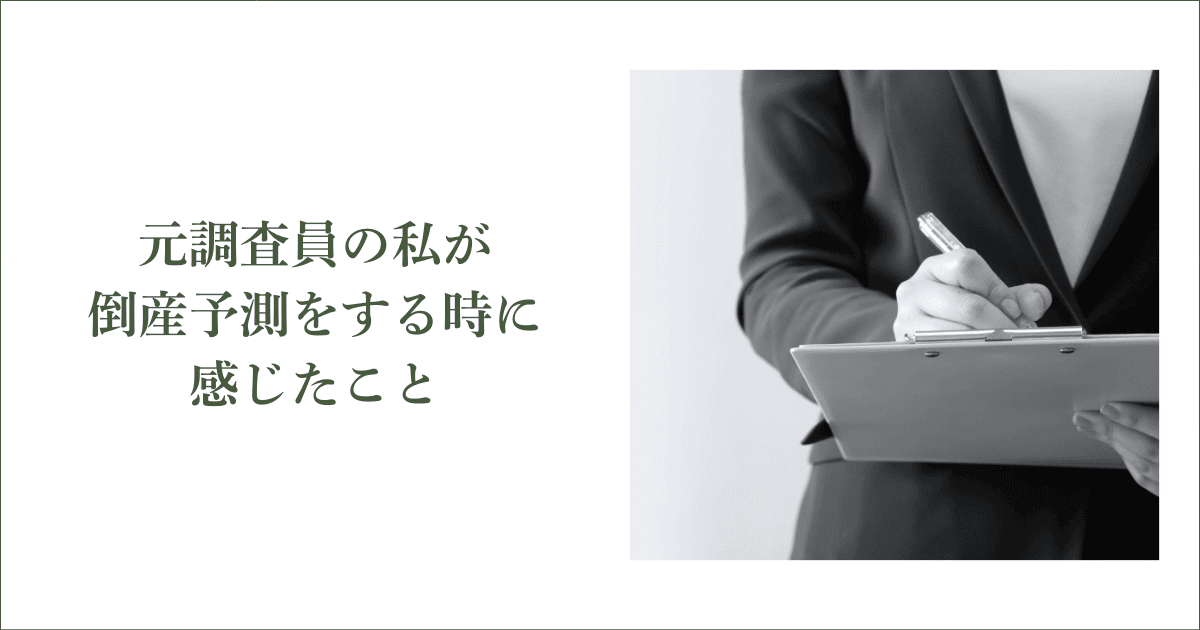
審査担当の皆さまは、いざ「この取引先は危ないかもしれない」という倒産の兆候をつかんだら、冷静に「倒産する可能性がある」と判断し、関係部署に取引中止や早期回収の指示を出すことができるでしょうか?
大変お恥ずかしい話ではありますが、私は新米調査員の頃、危ない状況を察知して対象企業の評価を下げる、倒産の危険性を報告書内で明確に伝える、その判断や報告に緊張や不安を感じることがありました。
冷静沈着に与信判断ができるようになったのは、3,000社を超える信用調査経験を積んだ頃であったと記憶しています。
「この判断は厳しすぎるのではないか。厳しい判断をして取引を中止して、万が一悪いことが起こらなければ、取引先との関係が悪化してしまうかもしれない…。かといって、もたもたしているうちに倒産してしまって、自社に損害が出たら困る…。」
恐らくいざその場面になったら、皆さまの頭にはこのような考えと不安が巡り、判断に苦慮することもあるのではないかと思います。
しかしながら、そこで覚悟を持って判断し、会社を守る決断をするのが与信担当者の責務。
そして、そのいざという場面での判断と決断を支えるのが、日々の与信管理です。
繰り返しになりますが、倒産を見抜くのは簡単ではありません。
日々の情報収集による小さな変化への気づき、審査担当者の豊かな知見と経験、確かな分析力、そしてそれを支える組織的な体制がなければ、確かな判断はできません。
本記事がその管理体制の構築に少しでもお役に立てれば、与信管理をご支援する者として嬉しく思います。
そして、皆さまの会社が安心・安全な取引基盤を築き、ますます成長していかれることを心から願っています。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
会社信用ドットコム代表 佐藤絵梨子
オンライン相談
与信管理のご相談を受け付けています。ご面談では、専門的な視点から具体的な解決策をアドバイスいたします。
ご相談内容を確認させていただき、無料または有料の初回面談や、具体的なご支援策のご案内を差し上げます。お申込みは以下よりお願いいたします。